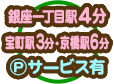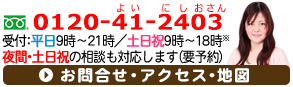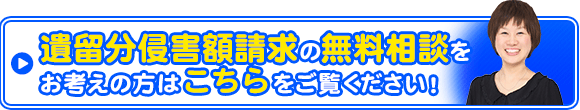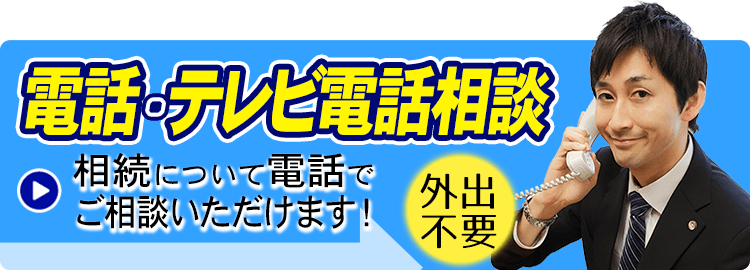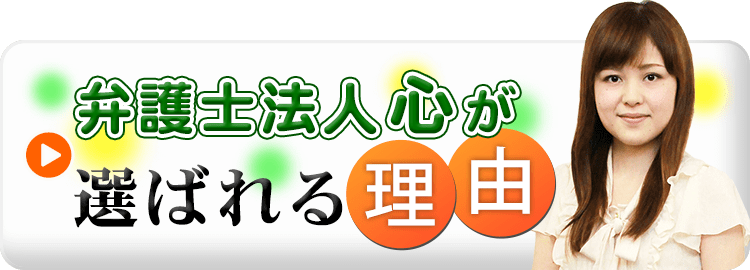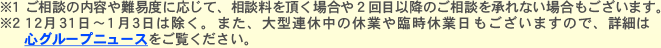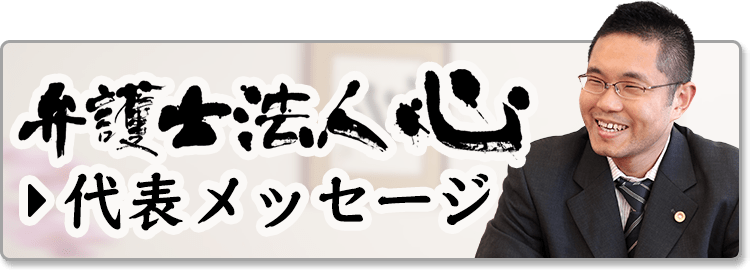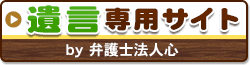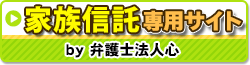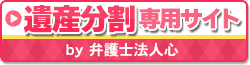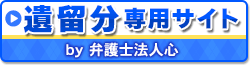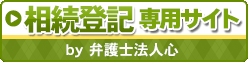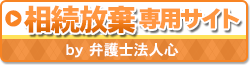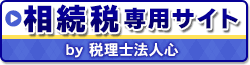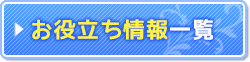遺留分の計算方法と具体例
1 遺留分の計算の仕方
遺留分権利者の遺留分の計算は、まず①の計算式で遺留分権利者が有する遺留分割合を求めます。
次に、②の計算式で遺留分権利者の遺留分を求めるという順序で行います。
①遺留分権利者が有する遺留分割合
総体的遺留分として定められた割合×遺留分権利者の法定相続割合
②遺留分権利者の遺留分
遺留分算定の基礎となる財産×遺留分権利者が有する遺留分割合(①)
2 総体的遺留分と個別的遺留分について
⑴ 総体的遺留分
総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分の割合のことであり、相続人の構成によって変わります。
具体的には以下のとおりとなります。
①直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合
総体的遺留分は3分の1です。
②直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合以外
総体的遺留分は2分の1です。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
⑵ 個別的遺留分
続いて、個別的遺留分は、個別の遺留分権利者に割り当てられる遺留分の割合ことをいいます。
遺留分権利者となる相続人が複数いる場合には、先ほど求めた総体的遺留分に対し、各相続人の法定相続割合を掛け合わせることで個別的遺留分を算定できます。
⑶ 遺留分の計算の具体例
例として、被相続人に配偶者と子3人がいる場合で遺留分の計算をしています。
まず、総体的遺留分は2分の1となります。
次に、配偶者の法定相続割合は2分の1なので、配偶者の個別的遺留分の割合は4分の1となります。
子の法定相続割合はそれぞれ6分の1なので、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ12分の1になります。
遺留分権利者が1人のみの場合は、個別的遺留分と総体的遺留分は同じになります。
3 遺留分算定の基礎となる財産について
遺留分算定の基礎となる財産は次の計算式で求められます。
(被相続人が相続開始時点で有していた財産)+(生前贈与をした財産)―(相続債務)
生前贈与した財産には次のものが含まれます。
①相続開始時(被相続人死亡時)からさかのぼって1年以内に贈与された財産
②1年以上前の贈与のうち、被相続人と贈与を受けた人の両方が、その贈与によって相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合の当該財産
③不相当な対価で有償処分された財産であり、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされたもの
④相続開始前の10年間に婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として相続人に贈与された財産
不動産しかない場合の遺産分割の方法 相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法